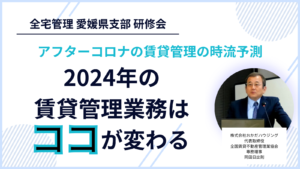はじめに:好印象の裏にある“違和感”とは
前編では、訪日外国人が感じた「安心・清潔・親切」な日本の魅力をご紹介しました。ではその一方で、彼らが戸惑いを覚えた“違和感”とはどのようなものでしょうか?
観光や短期滞在の印象にとどまらず、実際に住む/生活を始めるという視点で見たとき、日本にはどんな課題や工夫が必要になるのか。
今回の後編では、訪日外国人が語ってくれた“ちょっとした困りごと”や“文化のギャップ”にフォーカス。その中から、不動産管理業が担う役割や、未来へのヒントを紐解いていきます。
「食の選択肢」が少ないことへの戸惑い
メキシコ出身でカリフォルニア在住の女性は、日本のカフェ文化に触れてこう語ります。
「コーヒーを頼もうとした時、アーモンドミルクやオーツミルクといった選択肢がほとんどなくて驚きました。日本はまだ“牛乳ベース”が基本なんだと感じた。」
乳製品に対するアレルギーや宗教的背景、ライフスタイルとして植物性ミルクを選ぶ人も多い海外では、飲食における“選べる自由”が生活の質に直結します。
これは住宅設備や近隣の飲食環境にも当てはまる視点であり、「このエリアに住むと安心」と感じてもらうためには、周辺の情報提供も不動産管理業の大切な役割になるのです。

YORISOU TV:https://www.youtube.com/watch?v=bY8VX0UBSgY
子どもの“ひとり行動”に文化の違い
同じ女性が最も驚いたのは、日本の子どもたちの行動でした。
「小学生くらいの子が、1人で買い物していたり、電車に乗っているのを見て驚きました。アメリカでは、子どもだけで行動するなんて考えられない。」
これは治安の違いもありますが、「子どもを地域で見守る文化」がある日本ならではの習慣です。
外国人入居者にとっては、こうした“違い”を知るだけで安心につながることも多く、単に「ルールを守ってもらう」だけでなく、背景を共有する姿勢が求められます。

YORISOU TV:https://www.youtube.com/watch?v=bY8VX0UBSgY
言葉の壁は、“心理的な距離”にもなる
フランスから来た男女2人の声
「日本人は本当に礼儀正しくて親切。ただ、英語を話せる人が少ないので、もっと深く話したいと思っても難しいことが多かった。」
日本人の“丁寧さ”や“配慮”はしっかり伝わっている一方で、会話が深まらないことに対するもどかしさも印象に残っていたようです。
契約時の対応はもちろん、トラブル発生時の連絡、日常のちょっとした会話まで、言語の支援は物理的なサポート以上に、安心感や信頼感を生み出します。

YORISOU TV:https://www.youtube.com/watch?v=5517OkqFH0E
不動産管理ができること:違和感を“安心”に変えるために
多言語対応と背景の説明
契約時の翻訳はもちろん、「なぜそのルールがあるのか」といった文化背景の説明を添えることで、単なる“指示”ではなく“理解”につながります。
たとえばゴミ出しルールの背景にある「分別精度」や「地域住民との協力」の重要性を伝えることで、自然と協力意識が高まります。
暮らしに配慮した情報提供
- アレルギーや宗教に配慮した近隣飲食店の案内
- 短期滞在者でも快適な家具付き物件の紹介
- Wi-Fi環境や翻訳アプリの活用情報 など
「選べる自由」があることで、異文化の中でも自分らしい暮らし方が可能になります。
「孤立」しないためのつながり支援
言語の壁や文化の違いにより、外国人は孤立しやすい立場にあります。
イベントや交流機会の案内、相談窓口の紹介など、“つながり”を持てるきっかけをつくることは、生活全体の満足度に直結します。
不動産管理の仕事は、物件を管理するだけではなく、安心・快適・多様な価値観を包み込む“暮らしの器”をつくること。
まとめ:違和感を見逃さないことが、信頼を生む第一歩
今回のインタビューを通して見えてきたのは、「違和感」そのものが“よりよい暮らし”のヒントになるということ。
違和感に気づき、寄り添い、背景を理解しようとすること。
それが、不動産業として「選ばれる存在」であるために、最も大切な姿勢ではないでしょうか。
私たちの小さな工夫が、誰かの大きな安心につながる。
これからも、訪日・在住外国人のリアルな声を通じて、“まちと住まい”のこれからを考えていきます。
※本記事はシリーズ企画として継続予定です。次回もどうぞお楽しみに。