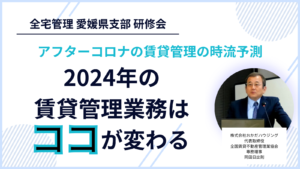2024年12月10日、一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会主催の「利益の組立図を作るための特別ゼミ」が長野県不動産会館にて開催されました。本ゼミには20名以上の参加者が集まり、活気あふれるセッションとなりました。昨年オンラインで開催された同テーマのセミナーも好評を博しましたが、今回はリアルな交流と実践的な学びを通じて、参加者同士の意見交換が盛り上がりました。

「利益の組立図」で解決できる課題
本ゼミでは、参加者が抱える具体的な課題を解決するための実践的なアプローチが示されました。主なテーマは以下の通りです。
・反響数や問合せ数が増えない
→管理戸数をゼロから1,200戸に拡大させた実例のご紹介も!受講後、数倍以上の反響を実現した方が多数!実践的な反響を引き寄せる方法を学べます。
・自社の強みを打ち出せず、大手に対抗できる自信がない
→消費者行動の理解を深めることで、他社との差別化戦略を構築し、独自のアプローチを確立できます。
・事業の次世代への引き継ぎが不安
→事業計画の重要性を学び、明確な将来像を描くことで、自信を持って事業を引き継ぐための方法を習得できます。
消費者行動を「見える化」し、実践するディスカッション型講座
「小規模事業者だから事業計画は必要ない」と考えがちですが、現代の消費者感性の変化に対応するためには、事業計画の策定が不可欠です。本ゼミでは、消費者行動を「見える化」し、循環させる方法を学びました。参加者はグループディスカッションを通じて、実際に自社で活用可能なアプローチを掘り下げて学びました。セミナー終了後も、会場内で活発な情報交換が行われ、参加者同士のネットワーキングが広がりました。
今回は講座の様子を少しだけご紹介します。

講座の流れ
・利益の組立図とは何か?(米澤氏)
・グループワーク①
・実践例のご紹介(中塚氏、佐伯氏)
地域No.1ブランドを目指す取り組み~管理戸数を0戸から1200戸まで拡大させた新規拡大方法~
・グループワーク②
講師のご紹介
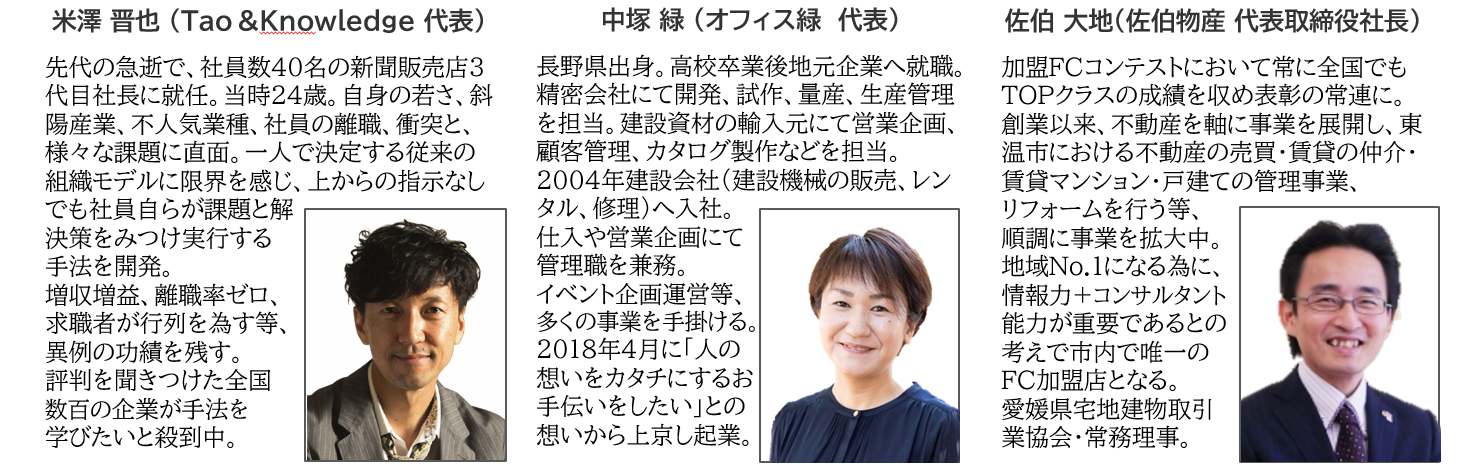
「利益の組立図」ゼミ 第一講:米澤氏が語る“人に寄り添う販促の極意”
「利益の組立図を作るための特別ゼミ」第1講では、米澤氏による「利益の組立図」の基本概念と、それを実践するためのアプローチが詳しく解説されました。この講義では、商品やサービスをたた“売る”のではなく、”お客様の幸せを創造する”視点からビジネスを再定義する重要性が説かれました。
利益の組立図とは?
米澤氏によると、「利益の組立図」とは、以下の3つの問いを通じて事業の全体像を明確にすることです。
- 何をもって(商品・サービス・ノウハウ)
- 誰の(顧客ターゲット)
- どんな幸せを創造するのか?
“誰が”、“こんな幸せを創造した”を増やす設計図になります。
人の感情と行動を理解することが成功の鍵
「モノが売れるという現象は、必ずその背景に人の“感情のゆらぎ”と“行動”がある」と米澤氏は示されました。具体的には、以下の流れが販促成功の基本です。
- 感情に火がつく:何かしらのきっかけで興味・関心を抱く。
- 行動が生まれる:お店に足を運ぶ、または問い合わせをする。
- 次の行動に繋がる:商品を購入する、契約を結ぶ。
ここで重要なのは、「モノを売ろう」とする視点ではなく、「お客様の感情に寄り添い、行動をエスコートする視点」に立つことです。「物ではなく”人”にフォーカスする」ことの重要性を繰り返し強調されました。
参加者は、このプロセスを通じてお客様のファン化を目指す販促方法を具体的に学びました。また、既存顧客の満足度を高め、新規顧客をファンに変える具体例も数多く紹介されました。
未来を売るという考え方
「お客様が購入しているのはモノではなく、自分の未来である」と米澤氏は述べます。
「何を持って(サービス)」「誰が」「お客様がどうなるか」「お客様がどんなセリフを口にするか」を具体的に設計することで、より明確な事業計画が可能になります。
講座ではこの設計を深堀りするために、参加者がワークシートを活用し、自社の強みを整理しました。具体的な販促方法やファン化のアプローチを議論しながら、自社に応用できる「利益の組立図」の初期設定を作り上げました。
最後に、米澤氏が講義を通して繰り返し強調したのは、「物を売るのではなく、お客様の未来を創造する」ことの大切さです。事業者が提供する商品やサービスは、お客様の「幸せの設計図」を描くための手段にすぎません。その視点を持つことで、真に顧客に寄り添う販促活動が実現できるのです。
利益の組立図ゼミ 第二講:お客様の心を動かす「動機付け」
どんな業界においても「商品やサービスを提供する」ことは、あくまでも手段です。本当に重要なのは、その先にあるお客様の幸せを理解し、共感を得ること――つまり「動機付け」です。
「利益の組立図ゼミ」第二講では、講師の中塚氏が「顧客の心を動かすための動機付け」について解説。共感を生み、行動につなげるための視点や具体的な取り組み方を学びました。
顧客の目的と手段を理解する:動機付けの本質
「誰の(顧客ターゲット)」「何を持って(商品・サービス・ノウハウ)」「どんな幸せを想像するのか?」これは第一講で学んだ利益の組立図の基本要素です。
中塚氏は、この中でも「何を持って」の部分における動機付けの重要性を強調しました。
例えば、大家さんがアパート管理業務を不動産会社に依頼する理由は、単に管理業務を依頼することが目的ではなく、その先にある「家族との時間を確保する」「家族に負担をかけない」ことが真の目的です。このように、「商品・サービス」→「解決されること」→「得られる悦び」が顧客の心を動かし、行動を促進する原動力となります。この視点を忘れてしまうと、不動産会社と大家さんの間に目的と手段のズレが生じてしいます。
他にも講義の中で参加者は、「他の顧客がどこで行動を止めているのか?」「どの部分に不安や疑問を感じているのか?」といった視点を学び、さらに、情報をデザインする方法として「伝えたいことを整理し、心に届ける方法」も学びました。
「人が先、物が後」―動機付けの真髄
中塚氏が伝えた最大のポイントは、「人が先、物が後」という視点です。
顧客が何を望んでいるのか?その「悦び」に寄り添うことで、自然と心が動き行動につながると強調しました。
第二講では、実際にさまざまなテーマやシチュエーションを通して「お客様の心の動機付け」を考えるディスカッションが行われ、参加者同士で意見を出し合い、具体的なアプローチを深掘りすることで、すぐに現場で活かせるノウハウを共有しました。
このアプローチを日々の業務に活かすことで、顧客の心を動かし共感を生む不動産のプロへと成長できるでしょう。
利益の組立図ゼミ 第三講:地域No.1ブランドを築く!~管理戸数0から1,200戸まで拡大した戦略~
「地方では商圏が狭く経営が難しい」――これはよく耳にする言葉です。しかし、工夫と継続的な取り組み次第で、地域№1ブランドを築き上げることは可能です。
「利益の組立図ゼミ」第三講では、管理戸数0から1,200戸まで拡大した実績を持つ佐伯氏が登壇。成功のカギとなった「ファーミング活動」と「賃貸管理の強化」について、具体的な取り組み事例を交えながらご紹介いただきました。
ファーミング活動:地域を知り、信頼を築く
ファーミング活動とは、特定のエリアを徹底的に調査し、情報を収集・管理しながら人脈を広げる営業活動です。佐伯氏は、管理戸数が0の時代から地道にこの取り組みを続け、現在では「地域の不動産といえば佐伯さん」と自然に名前が挙がるほどの信頼を得ています。これにより物件所有者や遠方に住むオーナーからの相談も増加し、地域密着型の事業展開が新たなビジネスチャンスを生む基盤となっています。
地域理解が成功のカギ
地域で信頼を得るためには、担当エリアの特性を深く理解することが重要です。地域の不動産市場の状況や住民ニーズを把握し、それを日々の活動に活かすことで、提案の質を高め、信頼を築くことができます。この地道な取り組みが結果的に地域№1ブランドの確立に繋がると、佐伯氏は語ります。
継続が生むブランド力
地域に密着した取り組みを愚直に継続することが、ブランド力の強化と地域№1の地位を築くカギです。佐伯氏は、「○○エリアなら○○不動産だね」と自然に名前が挙がるようになることを目標に掲げ、日々の活動を進めてきました。この姿勢が結果的に地域シェアの拡大を実現し、さらには新たなビジネスチャンスを生む基盤となっています。
参加者は、このブランド力を強化するための実践的なポイントについても学び、継続することの重要性を再認識しました。佐伯氏は次のように語ります。
「決めたことを愚直に続ければ、必ず結果は出ます。そして、困っている人は必ずどこかにいます。そこに気付き、寄り添うことが、不動産のプロとしての第一歩です。」
まとめ
「利益の組立図ゼミ」を通じて学んだ本質は、”顧客の心に寄り添い、信頼を地道に積み重ねる”ことです。ビジネスの軸を明確にし、地域に根ざして活動しながら、お客様の共感を得て心を動かすことで、顧客は行動に移り、その信頼はブランドへと変わります。共通する核心は、”人を先に考え、行動し続ける”ことです。お客様が求めているのは「不動産」そのものではなく、その先にある「幸せ」です。地域にとって必要不可欠な存在を目指し、今できる一歩を愚直に積み重ねていきましょう。
今回の内容に興味を持たれた方は、ぜひ次回の講義にご参加ください。新たな学びと発見が待っています。