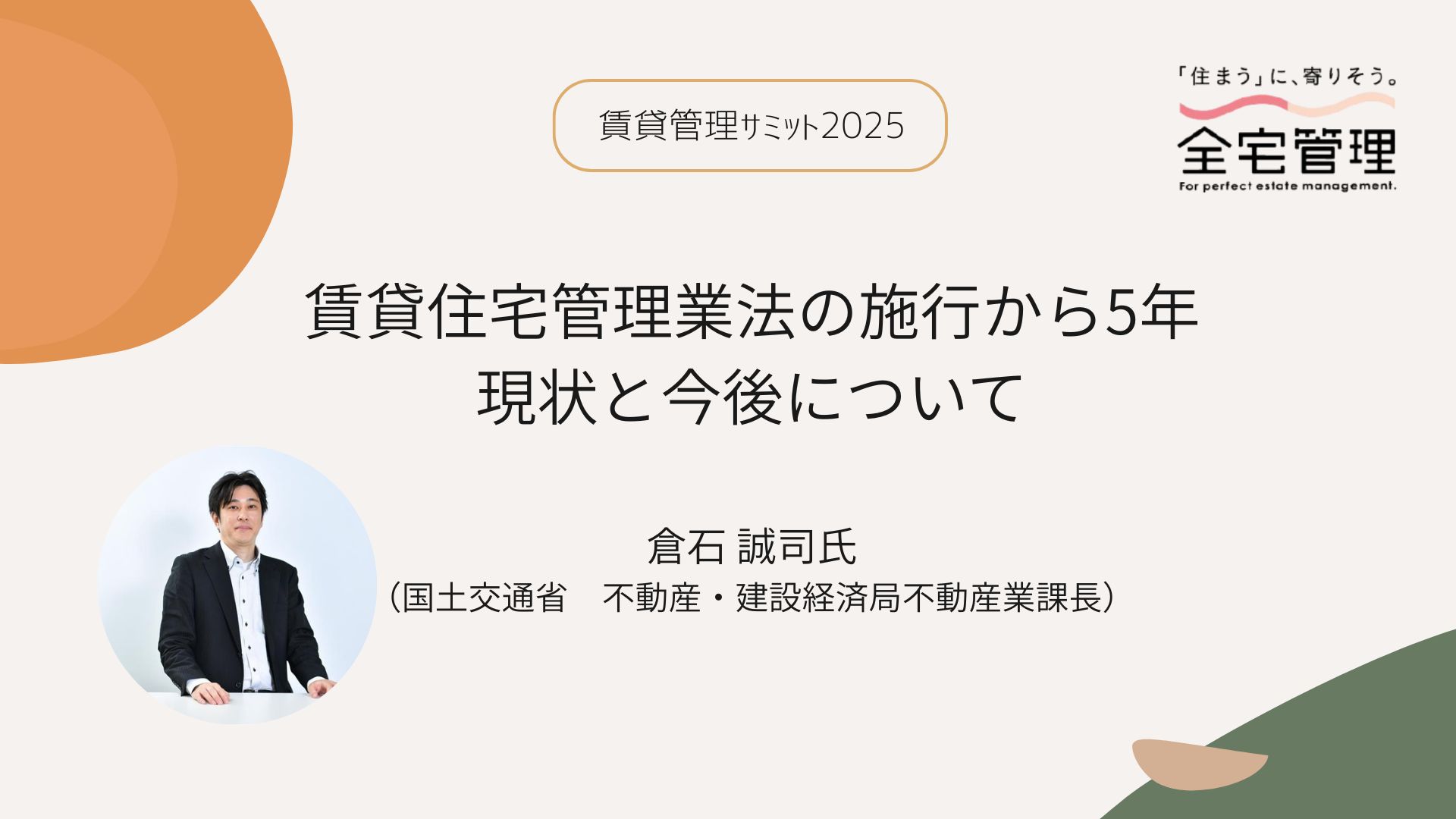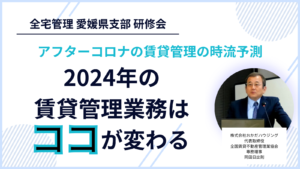本会では、賃貸不動産経営管理士有資格者の皆さま方に向けて、これからの時代を生き抜く知識や、業務の視野を広げるための情報が満載のオンラインセミナー「賃貸管理サミット2025」を開催しています。
今回の記事では10月14日(火)に開かれた第3回セミナー「賃貸住宅管理業法の施行から5年 現状と今後について」の様子をレポートいたしますので、是非ご覧下さい。
講師のご紹介
講師:国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課長 倉石誠司氏
プログラム
題名:賃貸住宅管理業法の施行から5年 現状と今後について
内容:賃貸住宅の管理業務の適正化を図ることを目的とする賃貸住宅管理業法が施行されてから5年目を迎えました。現在の登録状況について整理しつつ、立入検査や更新手続きなど含め、より適正な管理体制の構築が求められますので、今後の展望等についてお伝えします。
賃貸住宅管理業法が施行された背景
賃貸住宅管理業法は、令和3年6月に全面施行され、施行後3年が経過しています。
まず、法律ができた背景です。
賃貸住宅の重要性の増大、管理を委託等するオーナーが増加。さらに、“サブリース方式”の委託も増加という中、オーナーあるいは入居者とのトラブルが増加。特に、サブリース方式では、トラブルが多発し、社会問題化しておりました。そういった背景のもと、賃貸住宅管理業の登録制、サブリース方式の行為規制が制度化されました。
賃貸住宅管理業法の規制についてのご紹介です。
サブリース事業者への行為規制については、全てのサブリース業者に一定の規制を導入。勧誘を行う者も、規制の対象、違反者に対しては、業務停止命令等措置されました。
また、オーナーから委託を受けて200戸以上の賃貸住宅管理業を営むには登録が義務づけられ、業務を行う際は、業務管理者の配置、需要事項説明等が必要となりました。
法律の附則に、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
とありますので、今後検討をすすめる時期に入っているところです。
登録業者は約1万業者に
登録業者は一貫して増加傾向しておりまして、現在約1万業者となっております。
そのうちの3割から4割は、登録義務の無い管理戸数200戸未満の賃貸住宅管理業者です。
法律上、営業所ごとに設置が義務付けられる業務管理者の有資格者数は年々増加しております。
業務管理者の資格要件は、3つのルートがありまして、資格要件を満たす者は現在10万人を超える状況です。
なお、令和3年度に開始された新たな賃貸不動産経営管理士試験には、毎年3万人程度の方が受験しており、合格率は3割前後となっています。
令和6年度 全国一斉立入検査
国土交通省では、昨年全国187社に対して立入検査を実施し、127社に是正指導を行いました。
検査の結果、多くの指導事項がありましたが、全体的には形式的な不備が多く、全て改善が確認されております。
賃貸住宅管理業法が全面施行されてから5年が経とうとしていますが、まだまだ法令遵守が徹底されているといえる状況ではありません。
今後も、こうした検査を実施して法令の遵守を促していく予定です。
賃貸住宅管理業のあり方の検討に係る有識者会議の設置について
賃貸住宅管理業法の付則に見なし・検討状況が規定してあります。
アンケートや立ち入り検査で見えてきたものを踏まえ、今後の賃貸住宅管理業の在り方を検討するため、有識者会議が先月から始まりました。
主な検討事項は4つです。
①賃貸住宅管理業者が提供するサービスの見える化、賃貸住宅管理業としての報酬等
②賃貸住宅管理業の任意登録の促進
③業務管理者の資格要件のあり方、「賃貸不動産経営管理士」の社会的認知度の向上
④管理業の地域貢献(コミュニティーづくり、高齢者・子育て世帯・二地域居住者・外国人など多様な主体の共生社会の形成)
賃貸住宅管理業者が提供するサービスの見える化、賃貸住宅管理業としての報酬等
まず1つ目、賃貸住宅管理業者が提供するサービスの見える化、賃貸住宅管理業としての報酬等について
賃貸住宅オーナーへのアンケートで、管理業者とのトラブル内容について尋ねたところ、「管理業者が、どこまで対応してくれるのかよく分からない」という回答が最も多く、管理業者がどのようなサービスを提供してくれるのか、オーナーにとってより明らかにしていくことが求められています。
国交省の管理業務の見える化に関する取組みとしては、管理業務の内容、契約期間及び管理報酬など契約に関する重要な項目を明確にし、トラブル防止と双方の円滑な取引を目的として、賃貸住宅標準管理受託契約をリリースしているところです。
賃貸住宅管理業の任意登録の促進
2つ目、賃貸住宅管理業の任意登録の促進について
賃貸住宅管理業法は、管理戸数が200戸以上の場合に管理業登録を義務付けており、任意登録とは、管理戸数が200戸未満であるため、法の義務付け対象ではないものの、管理業法の登録を受けているものをいいます。
任意登録であっても、登録されれば、法の規制の対象となり、業務管理者の選任、オーナーへの重要事項説明・定期報告など、様々な義務が生じます。
トラブルの未然防止に繋がることから、国土交通省では、解釈・運用の考え方において、任意登録を推奨しています。
オーナー側からみて、管理業者を選ぶ際に重視する点については、対応の丁寧さやトラブル対応の迅速さ、委託費などが中心ではありますが、「賃貸住宅管理業者登録制度に登録している」との回答も約17%みられており、オーナーにとっても、管理業登録の有無が一定程度認識されていると考えられます。
これに対して、入居者の認知度は、賃貸住宅管理業に登録されているかどうかについて、「知らない」が86.7%と、認知度は非常に低い状況となっています。
このように、近年、任意登録は進みつつあるものの、さらに任意登録を進めるためには、オーナー及び入居者への認知度を高めていく必要があると思われます。
業務管理者の資格要件のあり方、「賃貸不動産経営管理士」の社会的認知度の向上
業務管理者は現在宅建士ルートと賃貸不動産経営管理士ルートの2ルートあります。
両方のルートをどうしていくかアンケートを取りました。
今後賃貸不動産経営管理士1本化にしていく理由としては、賃貸住宅管理の専門知識によりトラブル回避ができるからという意見が多かったです。
宅建士ルートを廃止しないでほしい意見としては人材の確保が困難との意見がありました。
宅建士ルートを廃止すると大きな影響があると答えた業者が2割程度。
今後是非について議論していきます。
あわせて賃貸不動産経営管理士の社会的認知度がまだまだ足りないので、向上させていく方法も議論していきます。
管理業の地域貢献
不動産業ビジョン2030で管理業の在り方を以下掲げています。
○「不動産最適活用」を根源的に支える役割
○幅広いサービスを展開し、居住・生活環境向上に寄与
○オーナーの投資判断の支援、管理情報の蓄積・活用
○従業員の働き方改善、管理業務の効率化や付加価値の高いサービス提供
国土交通省では、地方創生2.0基本構想、「ひと」と「くらし」の未来研究会とりまとめ、第4回地域価値を共創する不動産業アワード、「地域価値共創プラットフォーム」など様々な取組を行っています。
今後も注目いただければと思います。
次回のセミナー
今回のセミナーについて期間限定ではありますが、ホームページでアーカイブ動画を公開しています。
また来週以降もためになるセミナーを開催いたしますので、ぜひご覧ください。