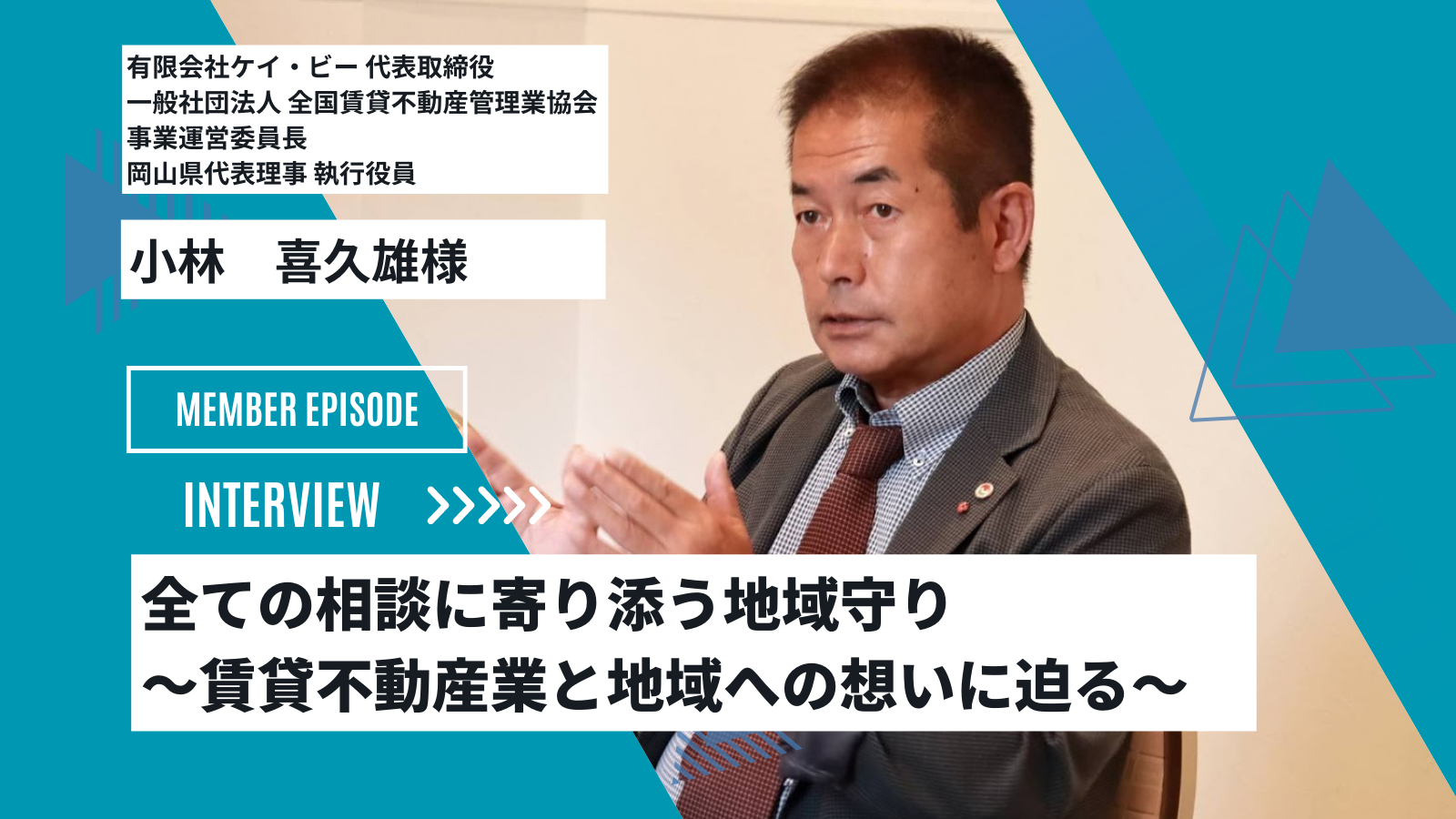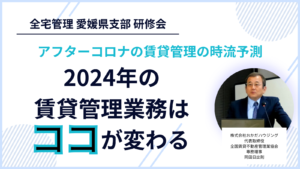賃貸不動産を通じて「住まう」に寄り添うメディア『YORISOU』が、全国の賃貸不動産会社の皆様に賃貸不動産の面白さや、地域への想いをお聞きする企画「Member Episode」。
今回は岡山県新見市に本社を構え、地域に寄り添って住まいに寄り添う、有限会社ケイ・ビーの小林社長に賃貸不動産業と地元・岡山県新見市への想いについてお聞きしました。

宅建の資格に興味を持ったことが不動産業を志すきっかけに
― 小林さんが不動産業に携わろうと思った背景をお聞かせください。
私が不動産業に興味を持ったきっかけは、近所に住む不動産会社の知り合いから宅建の資格の話を聞いたことです。その頃の私は18歳で、宅建や不動産業のことはもちろん何も知りませんでした。でもその方は「これから宅建の資格は役立つから勉強してみたら?早く資格を取るためには、東京に行って不動産業者に就職したらいいよ」とアドバイスしてくれて、行き先も決めずに東京に出てきました。
東京駅でアルバイト雑誌を眺めていたら、大手不動産会社の下請けで図面を作成する会社が目に留まり、連絡したらすぐ採用されることになりました。オフィスは丸の内の丸ビルにあって、東京に来ていきなりこんなところで働けるなんて運がいいと思いました。そこで2年ほど働く間に猛勉強して宅建の資格も取りました。
― 地元の岡山県新見市に戻ってから、不動産事業を開業されたんですね。
地元に戻っていきなり事業をやってもおそらく上手くいかないだろうと思い、最初は父が経営する会社の仕事を手伝いながら、不動産を兼業で始めました。そして父の会社の社名で開業して20年ほど経った頃、不動産の専業の会社になりました。父の社名で不動産業を始めたのと同時期に、地域の振興会に入って事務局の仕事を自分から買って出ました。事務局の仕事をすれば地域の民生委員や行政から情報が入ったり、地元企業とのつながりもできたりして、さらに深く新見市のことがわかると思ったからです。振興会の会長は2-3年ごとに変わりますが、私は40年間ずっと事務局を務めています。そのおかげで地域に寄り添ったサービスの提供が実現できていると思います。
― 新見市には学生さんも多く暮らしているそうですね。
私が新見市に戻ってきた翌年、新見公立大学が開校しました。看護や福祉を学ぶ大学で、2022年の大学クチコミランキングでは1位に輝いています。開校当初は280人ほどの小さな大学でしたが、今では全学部で800人ほどの学生が学んでいます。新見市はかなり特異な経済圏で、鳥取県との県境付近の町のため交通の便が良くなく、ほぼ100%の学生が市内に住んで通学しています。そのため岡山県下で家賃が一番高く、入居率が100%に近いのは新見市だと言われています。大学ができる良いタイミングで不動産業をスタートできたのは幸運でしたし、今ではありがたいことに学生の入居者のうち9割ほどのシェアを当社が占めています。ある大手の不動産会社さんは、人口がわずか3万人程の新見市に36棟ものワンルーム物件を所有しています。私たちの街は学生が多く入居するため、その影響もあるのでしょう、その会社さんの繁忙期におけるキャンペーンの営業成績では弊社が1位を二回も獲得しました。

引用:新見公立大学HPより
地域と入居者の生活、両方に寄り添うからこそ実現する手厚いサポート
― 貴社では居住支援が必要な方へのサポートもおこなっているそうですね。
開業してすぐは、サービス管理でスタートをして仲介業だけで成り立っている会社でした。家主がご高齢になった物件は「入居者を紹介してくれるなら、全部あなたに任せるよ」と言ってくださることが多かったですね。そういった物件を徐々に増やしていき、障がいのある方も外国から来た方も、どんな人でも私が家主さんに頼めば「あなたがいいって言うならいいよ」という信頼関係ができていきました。もちろん入居したら終わりではなく、色々な人が住んでいますからサポートは必須です。それらを処理しているうちに何でも受けるようになって、今では物件の全般的な管理をするまでになりました。
― お部屋が決まったあとも丁寧なサポートがある環境は、入居者さんも安心できますね。
一棟丸ごと弊社で管理をしており居住支援の必要な方が多く入居する物件がありますが、私はそのマンションの1階の部屋で寝泊まりしています。私が不在にする間はドアに電話番号を書いたメモを貼っておき、緊急時はいつでも連絡が取れる体制です。物件には様々な人が住んでいますが、例えば障害者の方で毎朝必ず8時に歌う住民がいます。8時になったらサザエさんの歌のワンフレーズを必ず歌うんです。最初はびっくりした入居者も多かったと思います。私もびっくりしました。ただ、本当に毎日8時に歌が聞こえるので段々と慣れてくるものです。反対に歌が聞こえない日にはみんなが心配になって私のところに連絡がくるようになりました。本来であればクレームになるかもしれません。ただ、個々の生活習慣がわかり、住民の顔が見えればそれを受け入れて結果的に入居者の方も見守ってくださる状態になりました。それぞれの生活習慣が分かれば「最近あのおばあちゃんのゴミの出し方が大丈夫かな?」などという変化が見えます。そういう方は必要に応じて民生委員と連携を取ったり、ガスや電気の業者が出入りをする際に様子を見てもらったりすることもあります。そうやって入居者の皆さんに寄り添い、地域にも寄り添った物件管理を普段から大事にしています。
― 地域にも生活にも寄り添うというお考えは本当に素敵です。
岡山県には1,300ほど不動産業者がいますが、残念なことに居住支援の必要な方へ部屋探しのサポートをする会社はまだ70社ほどしかありません。また、社名を公表すると問い合わせが多く来て仕事が増えることをマイナスに感じる方もいます。しかし、まだまだ住む部屋が見つからなくて困っている人は多くいますから、私は「どんな人にもできるだけ部屋探しをサポートしたい」と考える業者さんを見つけて、ぜひ連携を取っていきたいと思っています。また、どうしても紹介できる部屋がない場合でも「できません」と断るのではなく、当社をはじめとした居住支援に取り組む会社につなげてもらい、困っている人の相談先が途切れないネットワークができればいいなと思います。
バックグラウンドに関係なく、誰もが安心して暮らせる環境を
― 小林さんが地元の有志とともに行っている家賃保証の取り組みについて教えてください。
刑余者や、生活保護、高齢の単身者で保証人がいない方、または家族がいても連絡が取れない方は一定の割合でいらっしゃいます。そんな方でもお部屋を借りていただけるよう、地元のお肉屋さんの社長や食堂の経営者等の6人が出資し、保証グループという保証会社を作りました。新見市内の方だという情報さえあれば、その6人で保証しています。このサービスは一般の方にも提供されています。家賃滞納や住人が亡くなった場合は6等分して支払いますが、設立から10年が経ち、家賃の滞納等の大きな事故は一度もおきていません。
― 居住支援が必要な方も安心して暮らせますね。入居者の社会復帰については、仕事の斡旋など具体的にどのような配慮やサポートをしていますか。
仕事ができる状態の人なら、知り合いの会社に行って「この人に何か仕事ない?」と聞くこともあります。時には紹介した人がトラブルを起こすこともありますが、「もしよければ仕事を続けさせてあげて欲しい」と頼んだら、「小林さんがそう言うなら」という社長も有り難いことにいてくださいます。また市内の道を夜にフラフラしている若い人がいたら、声をかけて冷えたビールを一本あげます。それで笑顔になって帰る人もいれば、涙を流す人もいて、仕事に行きたくないと言う場合はそこの社長に連絡を取って「何かあって悩んでいるみたいだから、何日か休ませてあげたら」と連絡したこともありました。
不動産業は「相手の話を徹底的に聞くこと」から始まる
― 「こんな人に不動産業へ入ってほしい!」というお考えがあればお聞かせください。
いまだに不動産会社のお店は入りにくいイメージが先行しています。例えば、母子家庭の方が部屋を探していると言うと、いきなり「通帳を見せて」という同業者もいます。これは家賃滞納の恐れがない人を入居させたいという思いから出る行動ですが、本当に悲しいことです。お店に来た人は部屋を探している、つまり一種の困り事を抱えているわけですから、まず一言「今日はどうされましたか」とお聞きするのが大事です。不動産業界に必要なのは、そういう風に人の話が聞ける人です。法律を知っているとか人付き合いが上手いことよりも、対面して相手の話をしっかり聞くことが最も必要な力です。
特に母子家庭の方は、他の会社で断られて次々と不動産屋を巡って歩きます。断られたときの不安はずっと胸に残っていて、当社で「どうされたんですか」と聞くと泣き出す人もいます。そういう方にも安心して話してもらえるのが理想ですし、話を聞いたあとに当社ができることがあれば全力でサポートします。当社では第一声で断ることは絶対にしません。万が一紹介できる物件がなくても、何かできることはないかしっかり考えます。この人をどこへつなげばいいか、どこだったら相談に乗ってくれるだろうかと道筋を示してから帰ってもらうのを大事にしています。
― 小林さんが普段のお仕事で大切にする考え方は何ですか。
入居者に会ったときは、自分から挨拶して「何か困ったことはないですか」と聞くことを大事にしています。昔は入居者と顔を合わせるのが億劫で、何か言われるんじゃないかとヒヤヒヤしました。でもそれなら自分から聞いた方が楽ですし、相手に要望がある場合もない場合も、お互いの声が聞けたらホッとしますよね。
ですから私は家族にも「自分から声をかけて、挨拶だけでなく何かもう一言会話をしなさい」と教えています。会話があれば相手も要望を言いやすいですし、相手の様子から体調や機嫌も読み取れます。出かける方には「気をつけて」と必ず一言添えて、相手から「ありがとうございます」と返事があれば、気持よく一日がスタートできると思います。

誰もが快適に暮らせる新見市に!これからの町づくりでめざす姿とは
― これから新見市をどんな地域にしたいと思いますか。
新見市では8年ほど前、「日本一安心・安全な街づくり」をスローガンとしたことがありました。これは当時の新見市の警察署長が掲げたもので、その頃の市町村別犯罪率が最も低いのが新見市だったことに由来しています。それを私たちの保証会社のメンバー6人が受け継いで、今も様々な活動をしています。6人はそれぞれ事業を経営していますが、交通指導員など地域を見守る何かしらの役目を持って動いている人ばかりです。
― 地域と密に連携した活動を数多くなさっているんですね。ボランティアの地域清掃はどのような想いで始めたのですか。
当社はインターチェンジをおりてすぐの交差点に位置する、地域の中心地にある会社です。インターチェンジから当社までは150メートルほどですが、その区間は当社の玄関だと思っています。ですから、新見市の市街地でこの通りが一番きれいだとみんなに思わせたいのです。「まずは自分の身近なところから」と考え、地域清掃活動をFacebookへ投稿することから始めました。それで新見市民が気づいて、自分の会社や自宅の周辺だけでも掃除する人が増えれば、積もり積もって町全体がきれいになるのではないかと思います。

お孫さんもお掃除を手伝う姿 ※引用:小林様のFacebookより
― 長年にわたり地域に根ざした活動をされている小林さんの情熱の源は何ですか。
私の父が作り上げてきた地元の人たちとの信頼関係が非常に大きいと思います。不動産業を興すために地元に戻ってきたときも、多くの人が「あなた小林さんの息子さん?お父さんにはお世話になったよ」と親しく声をかけてくれました。そのたびに父の存在の大きさや、地元での人間関係を大事に育ててきた事を再確認して、私もそれを受け継いでいかなければと思います。今は私の息子や娘が仕事を手伝ってくれていますが、地域とのつながりは子どもたちにもしっかり伝えていきたいと考えています。

インタビュー中にそのお話に感動して何度も泣きそうになってしまいました。新見市とそこに住まう人たちを心から大切に想い、その情熱を具体的な取り組みにまで落とし込んで精力的に活動される姿を心から素晴らしいと感じました。本日は素敵なお話をありがとうございました。